WEBマンガやイラストを置いてあるサイトです。
※ただいま改装中のため見づらいうえ整合性ゼロです
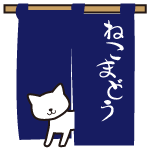
WEBマンガやイラストを置いてあるサイトです。
※ただいま改装中のため見づらいうえ整合性ゼロです
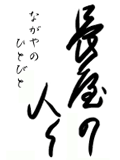
(一)
赤目令助が吉原へと続く日本堤を行っていたのは、夏も終わろうかという頃だった。総髪から下りる前髪はやや多く、顔の造りもあってか幼い印象をやや与える。だが花色の着物に墨色の馬乗り袴という地味な出で立ちは、周囲にそう違和感を覚えさせないらしかった。
昼の吉原は、夜よりも少しばかり艶やかさが欠けている。
ふと思い出したのは通を気取ったような言葉だが、言ったのは令助ではなく養い親の医者、応軒である。彼はかろうじて侍ではあるが、少年期の殆どをその応軒の元で過ごした。薬籠持ちのようなこともしたが、幼い彼を吉原に連れていくこともあった。
普段は神田の裏長屋に住んでおり、吉原の華やかさとは比べものになるわけもなく、道すがらが浮き足だった雰囲気となるのも、当然だろう。
だが令助が吉原に足を踏み入れたのは、あいにくと遊ぶためではない。吉原で三味線を弾く女に会いに来たのである。
名は薬煉という。芸者と言うよりは、女たちに三味線を教えている方が多い。古くは芸者は客と情を通じぬとされていたが、近頃は崩れてきているらしい。その中にあって、凛と気勢を崩さぬと言うのが、応軒に言わせれば「良い女」なのだそうだ。
しかし令助にしてみればこわい女という認識でしかない。そもそも女というのも気が引ける。何となれば、薬煉は令助にとって「師匠」なのである――。
「よく来たね、令助」
置屋の一角で薬煉がわずかに笑みを含んで言うのに、令助は頭を下げる。一目で年を当てるには少し難しい、おそらくは実年齢より若い見かけである。実のところ、令助も知らない。
「どうぞ」
令助が風呂敷包みを差し出すと、薬煉はそれをするりと解いた。現れたのは黒塗りの重箱で、開ければ茄子の煮染めがぎゅうと詰まっていた。
「良い茄子が入ったので」
「美味しそうだね」
その言葉に令助が口元を綻ばせる。それを見やって、薬煉は自信作なのだろう、と笑みを深くした。この「弟子」は真面目で面白味がない性格なのだが、こと料理に関しては趣味よりも一歩踏み込んだところに行く。やろうと思えば、それで身を立てることも難しくあるまい。
「変わりは無いかい」
「はい」
令助が頷く。わずかに視線をずらし、辺りに目を配る。この部屋に誰も来ないのは承知の上だが、癖のようなものであった。
「杉村様にも、特に変わりなく」
「近頃顔を見せないね。…まあ、さして寂しくもないが」
薬煉のその言葉を流しておいて、
「そういえば、外が少し静かでした」
「八朔が近いからね。ねだられて困るようなのが居ないんだろう」
ああそうか、と令助は頭を巡らせた。七月も間もなく終わる。衣替えが近いが、主はそこではない。
八朔とは、文字通り八月一日のことである。徳川家康が江戸城に入城したのがこの日のことで、大名や旗本などが江戸城に白帷子に長袴を付けて登城する。それになぞらえて、吉原でも遊女達が白の小袖をまとうのだ。芸者たちも新たに着物を新調するのだが、遊女の場合はそれを旦那衆に買わせるのである。
「滑稽な風情だねえ。白が似合わない連中がそろって着るなんてさ」
「師匠」
「杉村の坊やの白袴を考えただけで、腹がよじれるよ」
笑みを意地悪そうなものに変えた師に、令助はため息をついた。己の立場を全く気にしない発言である。
そもそも薬煉がこんなところにいるのも、杉村の要請によるものなのだ。
杉村雄之進。役目は表右筆であり、得体の知れない人物であるが、実のところは御庭番である。八代将軍吉宗が創設した、身分は下ながらも将軍に謁見できて意見も伝えられる、唯一のお役目である。
その杉村の元で働いている以上、令助も薬煉も、御庭番ではあるのだ。市井にあって耳目を働かせる。確かにそれには吉原は外せないだろうが、まさかそこでこんなことを言われているとは夢にも思うまい。
目の前の煮染めも元を言えば江戸城の蔵から出た金で作られているのだが――などと思う令助は、損な性分であった。
「令助。お前もまだまだだね」
「は……」
「静かなのは見た目だけ。内では少し、騒がしいよ」
薬煉の口元から笑みが消えているのを見て、令助の顔が引き締まった。
「何が?」
「遊女が一人死んだ」
あっさりと出た言葉に思わず薬煉の顔を見直した。切れ長の瞳に感情は見えない。
「だけど骸はない」
「ない?」
吉原で死人が出ることなど、そう珍しいことでもない。何しろ数千に及ぶ女たちがいるのだ。性病にかかって死ぬ者もいれば、無理がたたって死ぬ者もいる。心中なども珍しくない。火事などが起きれば、消火設備の整っていない昔では、より多くの死者を生み出すのだ。
だが、特殊な理由でもない限り、死体がない、と言うことはあり得ない。
「その前日から姿が消えてるんだよ。普通なら大騒ぎだ」
「……」
遊女はそもそも、人身売買の犠牲者である。やむにやまれぬ事情により、その身を買われる。そうして吉原でその借金を返すために働くのだ。
だが遊女の常、着物やかんざし、櫛や化粧品など、かかった金は全て借金に含まれる。それも生なかの品ではないし、積み重ねれば高額になる。
身請け――すなわち自由になるために大金がいるのは、そうした理由なのだ。
「消えたのは那須屋の雪緒。名前の通り、いつ消えてもおかしくないような娘だったけどね。お前、覚えてるかい?」
記憶をたどる。那須屋はこの見世の名だ。令助が薬煉に会いに来るのはここだと決まっているので、自然に顔なじみが増えている。気安く声を掛けてくる女や、わざとらしく袖を引こうとする女もいるのだが、令助はさすがにここで遊んだことはない。
雪緒、というのは人気の花魁であったと思う。顔は覚えていないし、話したこともないが、名前だけは聞き覚えがあった。
「足抜けでは?」
苦界を厭って逃げようと試みる者も中にはいる。捕まればひどい仕打ちが待っているが、それでも一縷の望みを抱くのは、無理もないことなのだろう。
「だったら隠す必要はない。…他の娘たちも口止めされてるようだね」
「死んだのは確かなんですか?」
「きっぱりと断言されたよ。…あれは、嘘なら出ない言葉だ」
思い出したように、薬煉が煙草盆を引き寄せた。閉め切った部屋に充満した香りが、強く令助の鼻を突く。
「お前、調べてくれるかい」
「はい」
令助が頷く。滅多にないことだが、師の頼みを断るわけにもいかない。それに、薬煉の立場を主人は心得ているはずだから、その薬煉が知らないと言うのはますますおかしい。
表に出せぬ事情はどの世界にでもあることだ。まして場所柄、公儀とはかけ離れていたい部分は多かろう。だが、――実はともかく、吉原は公認の遊び場なのだ。幕府の名を借りている以上、通さねばならぬ筋というものがある。
「礼は、そうだね。……ここの遊び賃くらいなら」
「失礼します!」
あわてて身支度を始めた令助に、薬煉は初めて笑い声を挙げた。
(二)
令助が初めに話を聞くことにしたのは、雪緒付きの禿であった。
「なんでござんしょ?」
幼いながらも身に付いた廓言葉で禿が答える。わずかに見覚えがあったが、少女自身の印象の儚さからか、はっきり名前までは覚えていなかった。薬煉から教えてもらい、廊下の端でようやく捕まえることができたのである。
「雪緒姉さんのこと」
優しく笑いかけながら問うたが、強ばった顔に口止めされているのは確かだと知る。ただ令助はここに何度も出入りしているし、警戒をされているわけではないらしい。
「俺、話した事はなかったけどさ。亡くなったって聞いて」
「……」
少女の手が震える。ぎゅっと握りしめているのは、櫛だろうか。少女が持つには古ぼけている。
「どっか悪かったのか、聞いてる?」
「違いおす」
小さな声に令助が身を屈める。周りには更に気を配りながら。
「病じゃない?」
「あい。姉さんは、亡くなりはったのやおへん」
「じゃあ、どうして?」
「姉さんは、神隠しにおうたんどす。せやなかったら」
少女は手の中の櫛に囁くように言っている。その声を拾うのは、令助とて難しかった。
「せやなかったら、あの人に――」
きしり。
廊下を踏む音に、令助が顔を跳ね上げる。それに驚いた禿が走り去り、令助は舌打ちをした。本来ならこんな廊下で聞く話でないのは分かっているが、死んだという遊女の部屋はとうに始末されている。落ち着いて聞ける場所はない。
何気なく廊下の先を見やって、現れた女に令助は見覚えがあった。
那須屋でお職を張っている――すなわち最も人気のある、花魁の夏緒だ。少しばかり険の強い顔立ちだが、派手目の美人なので令助も覚えている。
夏緒は何気なく歩いてきて初めて令助に気づいたように、おや、と声を挙げた。
「赤目様、お珍しい。こんな所で忍び会いおすか?」
すっきりとした声で、笑みも見せずに言うのは、令助が客でないのを分かっているからだろう。愛想を見せる必要がない相手には素っ気ないものである。
「まあね。夏緒にも話を聞きたいかな」
「髷を切られても構わへんのなら、ようおす」
鼻で笑って行き過ぎる夏緒に、令助はすれ違いざま、
「雪緒のことで」
その言葉は夏緒の足を止めるだけの威力はあったらしい。この女ならば、禿よりも知っているだろうか。
「師匠のお使いですえ?」
「さあ。ただちょっと、気になってさ」
「赤目様、あの子を買ったことが?」
「無いよ」
「なら、知らぬ顔する事ですえ。それでも知りたい言うなら、止めはおへん。あちきの部屋で、待っとうせ」
「部屋で?」
「ここじゃ都合が悪うおす。それに、ちいとばかりご不浄に用がありおすえ」
「……」
振り向けば確かに、厠の前であった。わずかに顔を赤らめながら去った令助の背を、夏緒はにらむように見つめていた。
「ほんに居はるとは」
呆れたような声に、令助はにこりと笑って返した。夏緒がため息をつく。誰が出したのか知らないが、令助の前にはお茶があった。禿が気を利かせたのだろうか。
「赤目様、ちいと勘が鈍くありませんえ。あちきは警告を」
「あれくらいじゃ恐がれないな。大体、俺はここで遊んだことはないんだし」
吉原には様々なしきたりがあるが、その一つに「浮気は厳禁」というものがある。同じ見世で違う花魁と遊ぶのは浮気に当たり、そんなことをした客には髷を切られるという仕打ちが待っている。実際にされれば長屋にはしばらく帰れないだろうな、とは思うが。
「なら」
夏緒がぐっと顔を近づける。赤くなって顔を背けるかと思った令助は、微動だにしない。ただ静かに見つめ返すばかりである。
「なら、はっきり言いおすえ。雪緒のことは忘れなせ。なまじ首を突っ込まれたら、那須屋が潰されおす。
そうなったら、赤目様、どうされるつもりえ」
「そうだな。どうして欲しい?」
「赤目様。あちきは本気どすえ」
「俺も本気だよ。まあ、何千両出せって言われても無理だけどな。一度首を突っ込んだからには、引く気はない」
「……相手は那須屋やおへん」
「その方がやりやすいよ、俺は」
「町奉行も相手に出来ない相手に、何が出来おすか?」
「だから、何をして欲しいんだ?」
「……」
夏緒が離れる。苛立たしげに座り込み、煙草盆を引き寄せて煙草を詰める。それも苛立っているせいかうまくはいかない。
その手から煙管を奪い、令助が煙草を詰めて返す。またにらまれるが、笑って返すと夏緒は深く息をついた。
「人が悪うおす」
「そうかもな」
「ふん。置屋へ来て遊びもしないで帰る無粋な小僧だと思うてありんしたが、とんでもないおすな。赤目様、いつも女子にそんな調子おすえ?」
「そんなってどんな?」
「……まっすぐ見つめるのは、想い人だけにしてくんなせ。心の臓に悪うおす」
それは夏緒の本音だったのだろう。深く煙草を吸い、ようやく落ち着いたらしい。
「そう。悪いことしたかな」
「子どもでもあらへんのに。今度あちきをそんな目で見るときは、お金を用意してからにしてくんせ」
「初会も持たないよ」
苦笑した令助に、夏緒が煙管を置いた。
「それで、なにをお聞かせざんしょう」
「何でもいいよ。知ってること」
「雪緒の月の話でも?」
「月?」
聞き返した令助に、夏緒がたまらず吹き出した。一瞬遅れて理解した令助が今度こそ赤くなる。
「勘弁してくれよ」
「品のないことを申しましたえ」
「夏緒、」
「ようおす。話しますえ」
夏緒がにこりと笑う。愛想が乗れば、冷たい顔つきが一変して、さすがに見とれるほどだ。
確かにお職を張るほどではあるが、騙された気分があるのは、自分が粋ではないだろうか。令助の頭の端をよぎったのは、そんなことであった。
(三)
雪緒は、雪国の生まれであったという。もともと生活の苦しい村を女衒と呼ばれる人買いが訪れ、幼く美しい娘を買うことは多い。
「売られたのは、五つの時とか聞きおした」
子どもの頃から、少しでも高く身売りをするために鍛えられる。雪緒も、語る夏緒も同じである。
「お師さんは、雪緒の三味線の腕を惜しがっておしたえ」
「惜しがって、というか」
薬煉が雪緒に関して言っていたのは、儚げな美人であったこと、強く出る性格ではなかったことと、
――あの娘は、諦めが早いからねえ。
そのひとことである。
芸を鍛えるには、幾度も壁にぶつかり、越えていかなければならない。止めてしまえば、それまでの腕で終わる。
諦めなければ、更に進むことも出来たろうに。
「いつでもそうおした。だからあちきがお職を張ることになったときも、おめでとうの一言ですませおした」
「おめでとう?」
「あちきとは同じ頃に見世に入りましたえ」
吉原はただ華美なだけの場所ではない。そのうちにはやっかみも憎しみも、当然のようにあることだろう。
雪緒はそうやって、全てを諦めてきたようだった。
女衒に売られることも。
三味線の腕も。
見世で職を張ることも。
そして、また――
「のし上がることが、雪緒には出来おへんどした。それでも、赤目様。そない女子の方が好きな方もおらはるやろ?」
「まあ、ね」
どちらかと言えば、令助もその方が好みではある。
「雪緒は大人しゅうおした。そないところが好みのお人には、我が物顔で振る舞うようなのもいはります」
「……」
さりげなく釘を刺された気分になったが、口を挟まないことにした。英断である。
「その、我が物顔を、雪緒がひっぱいたことがありんす」
「え?」
驚いた顔の令助に、夏緒が軽く笑って見せた。
「ほんまにひっぱいたんやあらしまへん。まるで自分の庭のように見世を歩く我が物顔が、禿を蹴り倒しおして」
「禿を?」
雪緒のでも、夏緒のでもない。だがそれを目撃した者は大勢あった。それでも誰も言わぬのを良いことに、更に手をあげようとしたのだと。
そこで、雪緒は言ったのである。
――旦那はん、その娘を殴りおすなら、父上様にお願いして、耳をそろえて五百両持って来てからにしてくんせ。
「五百両って、」
「その禿の借金、にしてはちと高うおすえ。まあそこは出任せでしょう。ただ、その我が物顔が付けてた見世代、それも含めればそれくらいになるかもおすな」
つまり、自分のものでないくせに、まして自分で身銭を切っているわけでもあるまいに、なにを偉そうなことを、と。
雪緒がその我が物顔を愚弄したということである。
「あれには胸がすっとしたえ。……その禿が、さっき赤目様が捕まえてた禿ですえ。あの娘はその後、雪緒の禿になりおした」
「夏緒が疑うのはその客か」
「刀二本差せばよろめくようなお侍でしたえ。面目を潰されて、あれっきり姿は見ておへん」
「雪緒がいなくなった時も?」
「あちきは。……赤目様。あちきは雪緒には生きていてほしいんえ」
「……」
「それが無理なら、諦めさせてくんなせ。あちきは諦めが悪うおす」
身を売ろうと、どこまで堕ちようと、石にかじりついてでも。
夏緒はそれを出来るという。
けれど雪緒は。
「俺は、その方が好きだよ」
「――」
絶句した夏緒に笑いかけて、令助は部屋を出た。他の誰か、もしかしたら店主に話を聞きに行くのだろう。夏緒の言に従うのならば、その客の素性を明かしに。
本当はそれこそを止めたかったのだ。死んだことは確かだと夏緒は聞いたのだから、重ねて他の誰かに聞く前に、令助を諦めさせたかったのだ。
なのに、令助の言葉一つと笑顔に阻まれた。手練手管に長けた花魁が、ただその一瞬に。
「人の言うこと、聞かぬお人おす」
自覚がないだけになお悪い。そう思いながら、夏緒はどこか楽しげな笑い声を漏らした。
「――何ですって?」
令助の問いに思わず返したのは、遣手婆である。客に遊女の采配をする役目の女だ。婆とは言っても、那須屋の遣り手は三十過ぎと言うところであろう。元々遊女だっただけあって、化粧をほとんどしていなくても、往事を偲ぶことが出来る。
「だから、雪緒の話」
「赤目様、その話は」
少しばかり慌てて袖を引いたが、令助は戸惑う様子も見せない。代わりに遣手の耳のあたりに顔を寄せ、
「最後の客の話だけで良いんだ」
囁くように言った。いつの間にか肩に手を置かれ、互いの頬がすり合うほど近づけば顔色を伺うことも難しい。
遣手ともなれば色恋沙汰とは縁が無い、憎まれ役である。若い男が近づくのも久方ぶりだ。
かといってかつては鳴らした自分である。こんな小僧に負けるものかと、遣り手は大げさに肩を揺らし、
「最後?ああ、雪緒の最後の客おすな、思い出しましたえ、呉服問屋の番頭はんが」
「その次だよ」
ぞくりとしたのは、色気のせいではない。
顔の見えぬ令助が放ったその言葉が、ひどく冷ややかだったからだ。
「取った客じゃない。最後に雪緒に会いに来た誰かがいたんじゃないのか?
……侍とか」
「だ、誰がそんなことを」
抜き身の刀を突きつけられた気分だ。むろん、そんなはずはない。令助の両刀は帳場で預かっているはずだ。
だというのに。
――つう、と汗が背を伝った。
「急いだ方がいいんだ。雪緒のためにもね」
「ゆ、雪緒は」
「亡くなってる、ってね。何があった?」
「……赤目、様。どこまで知って」
ぎりぎりと必死に横目で見た令助は、その言葉にふっと笑う。緊張が解けた遣手がよろめくのを支えてやりながら、打って変わった柔らかい声で令助は呟いた。
「推測でしかないんだ。――確かめたいんだよ、俺は」
(四)
その日。
那須屋にあがったのは、一人の侍であった。見覚えはあった。以前に何度も来ていた客のお付きの者である。ただ、その客は那須屋の花魁が恥をかかせた時から来ていない。ゆえにその侍も、顔を見せなかった。
だが、一人で遊びに来るということもあり得るのだから、何の不審も抱かなかった。
「雪緒を」
その指定に、遣手は眉根を寄せた。吉原の遊郭には、すぐに行って遊べるところもあるにはあるが、茶屋から仲介が入るのが普通である。まして雪緒はれっきとした花魁なのだから、そうそう気軽に遊べる相手ではない。
第一、以前共に来ていた際、ただお付きの者は待っているだけではない。同じように遊んでいるのである。だとしたら決まった相手がいるというわけで、そうすると雪緒と遊べば「浮気」である。
廓内での浮気は御法度である。その指定を受けるわけにはいかなかった。
「いや、遊びに来たわけではない」
「は?」
「ちと、話がしたいだけなのだ」
「はあ、」
雪緒の身は空いている。出来ぬ訳ではないが、さりとてそう簡単に頷くわけにもいかぬ。ここにはここのしきたりがある。相手が二本差しだろうと、譲るわけにはいかぬ。困ったように見た先の楼主が腰を上げる。
だが、楼主が断ろうとした矢先。
「構いませんえ」
静かな声が割って入った。雪緒である。いつからいたものか、雪緒は静かで落ち着いた声音で言った。
「雪緒、」
「お話だけならよろしおすえ。……いらはると、思うてありんした」
「さ、左様か」
雪緒の言葉に、侍はわずかに動揺したようであった。よろよろと後に続く侍の腰の物を、遣手は奪うように預かった。
「それきり、あちきも雪緒を見ておへん」
「見てない?」
「あい。他に知っているとすれば、あの禿が」
「雪緒の禿?」
遣手が頷くのに、令助は少しばかり考え込んだ。
吉原から逃げ出すのは困難である。無論、過去になかったわけではないらしい。だが逃げおおせたという話はまず聞かない。
「そうか。ありがとう」
令助が離れると同時に遣手は壁に背を預け、安堵とも何とも知れぬ息を漏らした。
令助が雪緒のことを探っているというのはすでに廓の中で広まっているらしい。姿を見れば皆そそくさと隠れている。
普段ならば面倒なほどに絡みついてくる遊女たちまでそうなので、いささか寂しい。
「どうするかな」
「赤目様」
悩んでいた令助に声を掛けたのは、那須屋の楼主であった。令助はあまり知らないが、薬煉とは以前から顔見知りであり、ある程度事情を心得ている者である。
「那須屋さん。何か?」
「こちらへ」
硬い表情で促されれば、想像はつく。奥の部屋に通された令助だったが、頭を下げた楼主の言葉は意外なものだった。
「お願いいたします。どうぞ、雪緒の仇をとってくださいませ」
「仇を?」
呆気にとられた令助が返すのに、楼主は深く頷く。
「左様でございます。一から話せば長くなりますので、絞って言わせていただきますが、雪緒は、殺されたのです」
「誰に」
「お気づきでしょう。雪緒の馴染みで、禿に乱暴をして横っ面を叩かれた、あの侍にです」
正しくを言うのならば、あの侍の供に、だという。
「何を話したまでかは知りませぬ。ただ、禿が真っ青な顔で私を呼びに来たのです。行ってみれば、花魁の着物が血だらけで」
ただ体は、ひどく綺麗だったのだという。
「そのお付きは剣術が達者だったのでしょうな。花魁は小刀をただ首に一筋、それで息絶えて他には傷もありませなんだ」
腕はよいのだろうが、その侍もまさかそんなことに使うとは思ってもみなかっただろう。
「着物は、ええ、そのお付きが血を吸わせていたのです。少しでも畳を汚すまいと。そのように気の利く方だというのに」
すまぬ、と侍に頭を下げられたのは初めてのことだった。重たそうな包みを出して、侍は言った。
この五百両を持って雪緒を身請けしたい。
花魁も承知のこと。
「承知のことだって?」
「そうでございます。禿が聞いておるはずだ、と仰いますので、聞けば禿もそうだと言う。雪緒は分かって、殺されたのです」
「遺骸は――」
「私が密かに葬りました」
楼主が顔を歪める。
「私どもとて、気概はあります。人から蔑まれる泥水でも、女郎は皆その水を飲む他なく、我らもあえて飲んでいるのです。それを無体に犯されては、我らの筋が通りませぬ。ですが」
「弱みでも、握られてたのか」
「何、私が悪かったのです」
楼主は力なく笑う。
旗本が遊郭で借金を作るのはよくあることだ。仲介役の引き手茶屋はどれもがその借金に悩まされている。何しろ旗本は絶対に金を返すことは無いのだ。余りに酷ければ公儀に訴えることも出来るが、多くは損をし続けている。吉原は町奉行の管轄ではあるが、侍は取り締まれない。
問題はそれだけでは無かった。このことが外に知れ渡れば、確かに一時は那須屋は繁盛するだろう。物見高い客はどこにでもいる。
だが、それが過ぎれば那須屋は潰れる。
侍の強健に負け、むざむざと女郎を殺された話が広まれば、女衒だって近寄るまい。
この店の者も、遊女も、路頭に迷う。
だから。
「私が、五百両と引き替えに、雪緒を殺したのです」
「……春駒」
掛けられた声に禿が声を上げると、見覚えのある侍がいた。まだ若い、柔和な侍は、少しばかりためらいながら口を開いた。
「その櫛、雪緒のか」
胸に挿した黄楊に手をやり、禿が頷く。
「見てたのか?」
その問いには首を振る。
「姉さんが、見てはあきまへん、と」
「そうか。優しい人だったんだな」
「あい」
「なあ、春駒。俺は一つだけ、嫌なことを聞くけど」
「……あい」
「どうして雪緒は殺されることを承知したんだ?」
長い沈黙が降りる。禿は真摯な目の侍を見つめ、首を振った。
「あちきには、とんと」
「……そうか」
「だから、姉さんは、神隠しにおうたんやと、思いあした」
そうした方が良いのだと。
だが。
「あのお侍はん、あちきに言いおした」
「その侍は、……五百両持ってきた方か?」
「あい。提灯を持たれてました。ご立派な、家紋入りの」
「家紋入りの?」
少しばかり目を見開く。
提灯には必ずと言っていいほど、印が入る。ただでさえ道暗い夜に行きあうためのものだから、それがどこから来た者なのか、身分証明になるからである。普通は引き手茶屋のものを使うから、わざと家紋入りの提灯を使ったと言うことになる。
無地の提灯は幕府の高官のみが使うもの、屋号ならば店屋、役所ならばその印、そして武家ならばその家紋――
「お侍はんは、あちきに提灯を差し出して、言いおした」
良いか、よく覚えておれ。
これは三ツ藤と申すのだ。
よっく、覚えておくのだぞ――。
「そう、聞かせてくれおした」
(五)
「何じゃ令助、いきなり来て」
令助が応軒の元を訪れたのは、夕方近くなってのことだった。いつもなら近くに転がっている徳利に苦言を呈する令助だが、今日はそうではなかった。
「先生、武鑑を貸してくれ」
「あん?どこに置いたかのう」
禿頭を撫でつつ、応軒が奥に消える。武鑑は武家の家紋と名前の一覧が載っているものだ。かろうじてこの家に置いてあるのは、羽振りが良かった頃もあったということだ。
それは無論、応軒が吉原通いをしていた頃と同時期であり――
「令さん、いらはりませ」
柔らかな声音とともに、わずかな灯りがさした。応軒の妻のはつが、手燭に灯を点してくれたのである。薄暗い黄昏時は文字を読むには不便だ。
「ああ、ありがとう」
「……恋敵はお侍おすえ?」
「は?」
はつの突然の問いに戸惑っていると、くすくすと笑いながら、
「令さんから白粉の匂いがして、先生が武鑑を探しておす。てっきり恋敵を捜してるのかと」
「まさか、……残念だけど、違うよ」
令助が苦笑を返す。はつは不満げな表情を浮かべて見せた。
「長屋暮らしの浪人に無茶言うなあ、はつさん」
「……そうおすなあ」
恋敵だろうと何だろうと。遊女が相手の恋は、本気であってはならないのだ。吉原は一夜の夢を売る場所だ。そこに重きを置くようでは、身を持ち崩すだけ。
夢が実に出来るのは、ただ一握りの人間だけだ。
「あったぞ令助、こいつじゃな」
応軒が武鑑を手に戻ると、はつは席を外した。令助は借りた手燭を側に寄せ、丹念に捲っていく。
「お前、吉原に行ったのか」
「ああ。師匠にちょっと頼まれてな」
「ほう。相変わらず美人じゃったか?」
「俺に聞くなよ」
「つまらん奴じゃ」
鼻を鳴らした応軒が、ひょいと令助の手元を見る。動きがぴたりと止まっている。
「あった。……ありがとな、先生」
旗本、黒尾家。三ツ藤の家紋と共に、役職や屋敷の場所が記されている。
「それで、何をやらかしたんじゃ?」
返事が無いのに顔を上げると、既に令助の姿は無かった。開けたままの戸から秋風がひゅうと入ってきて、応軒はぶるりと身を震わせた。
秋も深まれば、あっという間に日は落ちる。令助がその旗本の屋敷に着く頃には、辺りは闇に包まれていた。ふ、と息を吐き、塀の側に身を寄せる。武家屋敷の辺りは元々人通りが少ない。怪しまれたわけでもなく、誰の気配も感じなかったが、それでもしばしの間、令助は身動き一つしなかった。
どこかで鈴虫が鳴いているのが聞こえる。さわり、と静かな風が袴の先をわずかに揺らした。
一瞬、令助の手が地を突き、次にはその体がふわりと塀の向こうへと躍っていた。虫の音が止む。かさりとも音は立たず、やがてりりり、と寂しげな音が再び響いた。
黒尾家の屋敷は、そう広いものでは無かった。一口に武士・旗本と言っても、役職や身分は様々だ。応軒の所にあった武鑑は古い物で、それには小普請組とあった。これはすなわち、無職であると言うことだ。知行は与えられているが仕事が無いから、ろくな事はしでかさない。金が無くとも吉原で借金を作って遊び、踏み倒す輩もいるという。
――五百両か。
身をかがませた令助が慎重に歩を進めながら、「我が物顔」が作った借金の額を思い起こした。それを出せるほど豊かではなさそうだが、いかにして作ったのだろう。
「――」
ふと誰かの声が耳に入り、令助は眉をひそめた。平常の話し声では無い。怒鳴り声だ。そっとそちらに向かえば、がたりと障子の桟が揺れる音まで聞こえた。おそらくどこかが壊れたのだろう、漏れ聞こえる声がわずかに大きくなる。
「馬鹿者が!なぜもっと早く言わなんだ!」
「申し訳ございませぬ、殿……」
「和馬めはどこにおる!」
「ただいま、伏せっております故、恐れながら……」
「何が病じゃ!たかだか遊女に懸想した挙げ句、叔父上にまで面倒を掛けおって!ぬしがついておりながら、愚かなことを……」
「申し訳ございませぬ」
「聞き飽きたわ!」
がたん、と先ほどよりは静かだが耳障りな音がした。何かを畳に投げつけたのだろう。
「わしが小普請組より抜け出るにいかに苦労したか、ぬしも分かっておろう!あやつはそれを台無しにする気か!」
「……」
「叔父上にも釘を刺されたぞ。いかに町奉行が我らに手が出せぬとて、文句がご老中に届けば木っ端のようなものじゃ、とな。禄を失いたくなくば、和馬は廃嫡せねばならぬ」
「そ、それは」
「これ以上何かあればの話じゃ。幸いにも一人遊女が死んだだけ故、大事は無いが……良いか、それをあやつにも詰と申しておくのじゃぞ!」
だんだんと強く廊下を踏む音が去り、静寂が戻る。かたりと障子が鳴ったのは、残された家臣も部屋を出た為だろう。話の内容からすれば、おそらくこちらが那須屋を訪れた侍だろう。
――腕が立つ、と言ったか。
侍が先ほどとは真逆の方へと進む足音が聞こえる。令助はそれをあえて追わなかったが、侍は途中でぴたり、と止まった。
「……為したことは、全て己に返るものじゃ。仕方も無いこと」
殿と呼んだ男に返した物とは全くと言って良いほど違う、厳しい声だった。
再び侍が進み、その気配が完全に消え去ってから。
令助はようやく身を起こし、じっと暗闇の先を見つめた。
白無垢を着た花魁たちの道中に、押しかけた見物人達は誰が綺麗だ、あの花魁は旦那様が羽振りが良いから見ろ立派なものだ、などと好き勝手なことを呟いている。
「おやあれは那須屋の夏緒かい。相変わらずきつい顔だな」
「なに、あれっくらいきりりとしてた方が良いさね」
「しかし、あの櫛はずいぶん古とぼけてるねえ」
その声に、そうだそうだと声が上がる。彼らの前を平然とした顔で通り過ぎた夏緒が、ちらりと視線を向けた先に、花色の着物があった。
だがそれも、瞬時のことで長くは止まらない。前に続いた春駒を見守るようにしながら、凜とした表情で、彼女は歩んでいった。
夏緒の姿が完全に那須屋に消えてから、最初に口を開いたのは令助ではなく隣にいた薬煉だった。
「あの黄楊の櫛、雪緒の形見だってね」
「らしいですね。……聞こえていたでしょうに」
「あれしきで揺らぐようじゃ、花魁とは呼べないよ」
薬煉の口調はいつになく優しい。苦界にある女達の境遇を、側でより深く知っているからこそだろう。
「つまらない物ですが、お土産です」
令助が袂から取り出したものを薬煉がちらりと見やる。懐紙に包まれて外からは見えないが、にやりと笑って手に取る。そのまま喧噪から離れるように歩き出した薬煉の後に、令助が続く。
「杉村の坊やから聞いたよ。何とかって家の跡継ぎが、病気を理由に廃嫡になったってね」
「そうですか」
「親戚筋から新たに養子を迎えるそうだよ。……髷を切られるなんて、怖い病もあったもんだ」
「全くです」
柵に囲まれた吉原の端、その先は更にお歯黒溝と呼ばれる濠で囲まれている。ここから出るには吉原の唯一の出入り口、大門を通るしか無い。余りにも狭い道だ。
「花魁はどこかの寺に埋葬されたようです。それがどこかまでは……」
「そうかい。まあ、投げ込み寺よりは幾分ましかも知れないね」
包みを軽く手で弄んだ薬煉が、おもむろにそれを投げた。高く宙を舞った後、ぼちゃりと音がして、泥に沈む。
「ご苦労だったね、令助。だがあいにくと今日は遊べないよ」
「小遣いなら要りませんよ」
「……なら、一つだけ言っておくけどね」
「はい?」
はあ、とため息。
令助が師の顔を見れば、呆れたような顔をしていた。
「お前、誑すならもう少し相手を選びな」
「……は?」
怪訝そうに眉をひそめた令助に、薬煉はもう一つため息をつく。言っても気付かないだろう事は分かっていたが。夏緒が三味線の稽古の後、薬煉に言ったのである。「お師さん、困った弟子をお持ちおすね」と。
急いでいた故とは言え、そして最も良いやり方だとは言え――これが玄人ではなく素人が相手だったなら、どうなっていたことか。
「まあ、良いさ。気をつけてお帰りよ」
「はい」
その思惑に気付かぬまま、令助は頭を下げて大門へと向かった。自分と同じ道を行く者はほとんど無く、すれ違うばかりである。町人も侍も、多くの者の顔を自然と目に入れながら、ふとあの家臣はどうしたのだろうと思った。
雪緒を埋葬させたのはおそらくあの家臣の采配だろう。それでいて、行いを止められなかったのだ。
腹を切ったやも知れぬし、そのまま勤めているやも知れぬ。
――だがどちらにしろ、令助にそれを悟るすべは、もはや無いのだった。